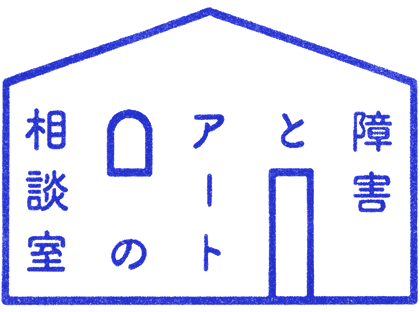レポート:トークシリーズ「障害のある人のアートと評価~第2回美学・哲学のものさし」

2016年11月18 日、トークシリーズ「障害のある人のアートと評価」第2回が開催されましたのでレポートします。
今回の講師は慶應義塾大学や京都造形芸術大学で活躍された後、現在は京都での新しい共同生活に取り組まれている熊倉敬聡さん。以下にその内容をまとめます。
--------------------
アートについてのトークでしたが、お話は熊倉さんご自身がここ最近アートに関わっていない、というところから始まっていきました。アートは今もう色々な意味で限界の局面にあると熊倉さんは感じておられ、そこから一度出る必要を感じていらっしゃるそうです。熊倉さんは今、自分とアートとの関係を結びなおす試みをされているそうで、そのなかでアートに対する新しい見方も模索されていました。
第一のものさし アートの自己目的性
近代のヨーロッパで生まれた「アート」というものは、19世紀の後半、その歩みのなかである限界を迎えます。熊倉さんが例にあげられたのがモネです。モネの若い頃の作品では写実的な表現で風景が描かれているのですが、後年の作品では、同じ庭の橋を描いているはずの絵画ですが、一見何を描いたのかわからない絵の具の色の集積のようなものになっていきます。これは、モネの関心が外に見える世界ではなく、絵の具の動きそのものやキャンバスが持つ強度のようなものに移っていったからではないか、と熊倉さんは考えます。「何かを描く」ことにではなく、「描く」ことそのものが目的となっていく。すなわちアートの自己目的化が起きます。この「描くこと」そのものの探求は19世紀末にとてつもないレベルに到達し、これ以上進めない状態に陥っていったそうです。
第二のものさし 反芸術「アートでないものをいかにアートにするか」
その限界をひしひしと感じていたアーティスト、たとえばマルセル・デュシャンは、トイレの便器をそのまま美術館に展示しました。この行為から一つの運動、「コンテンポラリーアート」が始まります。これはすなわち「アートでないものをいかにアートにするか」という試みであり、その精神が現代美術を支えた原理だと、熊倉さんは解します。まずはその運動はデュシャンの「既製品」のようなものからはじまり、そして、ついには「空虚」や「静寂」というものへ向かいます。そしてその後で、その運動の対象は、欧米の文脈にはないもの、日本を含めアジアやアフリカにあるものへと向かっていきます。ほんの20年前にはアートと呼ばれなかったものが、優秀なキュレーターに見出され、「大地の魔術師」展に代表されるように、欧米と非欧米の創作物が並列で並ぶようになっていきます。
第三のものさし 生活=美
西洋の文脈を少し外れると、別のものさしもあります。熊倉さんは柳宗悦の提唱した民芸についての考えを引きながら、生活の中にある美というのを語られます。柳によると、「用の美」というものがあり、日常の生活の垢にまみれてこそ磨かれるものがあるのだそうです。西洋アートの歩んだ「自己目的化」においては外の世界に関わらないことに価値がありましたが、この考えではその全く逆で、日常生活に役に立つものこそが価値を持ちます。生活がいかに美的なものに彩られているか、というのが民芸的な考えにおける重要なものさしだったそうです。
第四のものさし 気=エネルギー
最後に熊倉さんは、現在京都で営まれている生活の中で模索されている新しいものさしを提案されました。それが「気=エネルギー」です。大学を辞めてからの新しい生活の中で、熊倉さんは「暮らしに関わるものはできるだけ自分たちで作る」という実践をされているそうです。そうすることで西洋的なアートの文脈から出て生活の中に自分を位置付け直し、「作る」ことを見直している、とのこと。そうしてみてみると、作るということは人為だけでは成り立っていません。野菜ひとつとっても、自然も自らを「デザイン」していて、自然のデザインと人間のデザインが出会ったところに「作る」という営みが生まれています。そうした自然に溢れるエネルギー「気」がどれだけ創作物に入っているか、という風に見ることができれば、健常者が作っていようが障害者がつくっていようが、アート作品という文脈で評価されようがされまいが、あるいは野菜を作ることでさえも同じようにみる事が出来るのではないか。ある人がアートにどれだけ気を込めたか、魂を込めたかというのを測れたら面白いのではないか。そんな今後への提案で、熊倉さんは話を結ばれていました。
西洋の美術史的な話から始まって、最後に「気」に行き着いたときは、会場の誰もが驚いているようでしたが、不思議と納得の雰囲気もありました。最後のほうに話されていた、あくまでも気が入っているかが大事であって、「寿司は寿司だから全部おいしいわけではない。野菜も野菜だからすべて栄養があるわけではない。アートもアートだから全部良いわけではない」というお話は、とても当たり前のことながら、忘れてはいけない大切なことのように思われました。
(レポート:菊竹智之)

講師の熊倉さん

今回も沢山の方にお越しいただきました